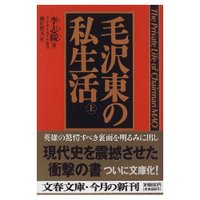 家の近くには古本屋のチェーン店Book Off があるため、会社の帰りや出かけたあとには、ちょっと立ち寄ることが多い。新刊だと高いが、古本屋で買うと激安だったりする場合があり、特に新刊では絶版になってしまったものも、たまに古本屋で見つけられる場合もあるから重宝している。本書に関してもまさしくそんな本の1冊で、新刊ではもう手に入らない。家の近くのBook Off ではなんと1冊100円で売られていたので、思わず手にとって買ってしまった。噂では聞いていたこの本。実際に読んでみると、これを書いた著者が殺された理由もわかるというものだ。「英雄」とか「神様」と信じていた人の悪口や、神格化してしまった人間を再度人間化してしまったのであれば、虚像のように崇めていたことをすべて崩壊させてしまうために、こういう暴露本が出てくると言う事は、その信者にとっては悪書そのものである。従って、当時の中国共産党政権の密令により、アメリカのニューヨークに逃亡していた著書が殺されてしまうのは当然の成り行きだろうと思う。著作が発表された後、「本の内容は事実無根である」とお決まりの「全否定」を徹していた共産党も、さすがに嘘をつきつづけることは困難だと判断したのだろう。中国の歴史は毎回だいたい同じで、嘘が隠せなくなった場合は、それをさらに拡大しないようにすることに次は努める。第2段の暴露本を出される前に、「嘘」と言わざるを得ないことを生成する根源を抹殺することが重要いうことになる。この本と著者の関係は、中国の政治的なやりかたと惨殺さについてを、出版後に全世界にも分からせることになった。
家の近くには古本屋のチェーン店Book Off があるため、会社の帰りや出かけたあとには、ちょっと立ち寄ることが多い。新刊だと高いが、古本屋で買うと激安だったりする場合があり、特に新刊では絶版になってしまったものも、たまに古本屋で見つけられる場合もあるから重宝している。本書に関してもまさしくそんな本の1冊で、新刊ではもう手に入らない。家の近くのBook Off ではなんと1冊100円で売られていたので、思わず手にとって買ってしまった。噂では聞いていたこの本。実際に読んでみると、これを書いた著者が殺された理由もわかるというものだ。「英雄」とか「神様」と信じていた人の悪口や、神格化してしまった人間を再度人間化してしまったのであれば、虚像のように崇めていたことをすべて崩壊させてしまうために、こういう暴露本が出てくると言う事は、その信者にとっては悪書そのものである。従って、当時の中国共産党政権の密令により、アメリカのニューヨークに逃亡していた著書が殺されてしまうのは当然の成り行きだろうと思う。著作が発表された後、「本の内容は事実無根である」とお決まりの「全否定」を徹していた共産党も、さすがに嘘をつきつづけることは困難だと判断したのだろう。中国の歴史は毎回だいたい同じで、嘘が隠せなくなった場合は、それをさらに拡大しないようにすることに次は努める。第2段の暴露本を出される前に、「嘘」と言わざるを得ないことを生成する根源を抹殺することが重要いうことになる。この本と著者の関係は、中国の政治的なやりかたと惨殺さについてを、出版後に全世界にも分からせることになった。 1949年の中華人民共和国設立以降、図体がでかい割りに、中身がからっぽの国ができたのは、すべて共産党政権の無能さと内部の政治的闘争のせいだといわれるが、そうではなく、単に「毛沢東王朝」であっただけで、単なる1人のデブオヤジの妄想のもとに10億人の無能がついていっただけのことである。実は無能だということがバレル前に、いわゆる知識層を一番最初に抹殺したことが上げられる。そこから始まった政治闘争は、その後に残った馬鹿たちが神様毛沢東に「どうしましょう?」と頻繁に伺い、顔色を伺いながら政治を行っていたことになる。その現場のすぐ傍で医者として活躍していた著者は、英語の教師として最初毛沢東の身近に接することになるが、その後、西側諸国で教育を受けた著者から西側の情報と当時の中国の知的レベルの違いさを歴然と反省し、どうすれば中国人が優秀になれるかを模索していた毛沢東の相談役になっていったことから、毛沢東の信頼性を掴んでいった。毛沢東の信頼を受けていた政治に関係ない医者になってしまったおかげで、政治闘争の枠に必然的に引き込まれてしまう。つまり、毛沢東の顔色を窺っていた馬鹿政治家たちが、この医者を巻き込むことで、自分を優位にたたせたかったという腹積もりがどの政治家にも存在していたからだろうと思う。一番顕著なのは、毛沢東の妻にして無能だったためしばらく政治の世界に入ることが許されなかった江青だろう。江青と著者の間の陰湿なやりとりについては興味につきることはない場面だと思う。現在、「マダムマオ」という本が出ているが、それを読む前にこの本を読んで欲しいと思う。
毛沢東の自己の権威を保持するために発動された文化大革命。これまでは社会的不満の爆発の結果だと思っていたのだが、実際には違ったことがこの本を見て分かった。旧ソ連との関係がわるくなったのも、スターリン後政権によるスターリン批判が中国に伝播し、そのまま毛沢東批判を身内からでないために、あえて中国とソ連とは共産党のイデオロギーが違うのだと述べているところが、単なるわがままなガキの身勝手さで国の運命を左右させていったことがよくわかって面白い。さらに毛沢東の影のサポータとして活躍した周恩來との関係についても、この本を見るとよく分かる。数多く周恩來に関する単独の本は存在するが、あまり人間臭い部分を覗かせた毛沢東と周恩来の関係を述べている本は無いと思う。そういう普段の人間では知ることが出来ない政治の舞台裏を、医者という立場ですべてを知ってしまった著者は、有る意味かわいそうだと思われる。肉体的には、いつ何時毛沢東から呼ばれるかもしれないということから、十分な睡眠は取れないし、旅好きだった毛沢東のわがままで予定未定の長距離旅行(表向きは視察)に付き合わされたり、女好きでセックス好きな毛沢東の性病を治すために数々のアドバイスをするが、言うことを聴かないわがままな患者につきあわされなければならないし。手術をする必要があるような病気に毛沢東が掛った場合も、毛沢東がもしいま死んだら、誰が今後の政権を握らねばいけないか、または握ることができるかという政治闘争が始まるから、側近から手術だけは許さない!と意味不明な抵抗に有ったりと、22年間の主治医としての生活はハード極まりなかったと思われる。
中国共産党の歴史を知るためには、中国共産党が自ら出版した本を見るのは危険である。なぜなら嘘ばかりしか掛れていないからである。全世界が既に知っていることであっても、それはすべて嘘であると平気で言うし、党の指示はすべて正しいといわねばならないという脅迫観念で13億の人間を動かしている「人治国家」(通常の国家は法治国家)を続けるためには、内部的にはすべて正しいということにしておかないと矛盾が出てきてしまう。従って、外部の目で、むしろ、元々内部の人間だったが、現在は外部にでて好きなことが言える環境になったひとからの情報が一番重要である。本書はそういう意味では、内部の内部に入りこんでいて、その随時変化していく内容を正確に記載していることは驚きである。毛沢東の政治はすべて正しかったということにしたい中国共産党にとっては、悪書以外何者でもないと思いたいはずである。40年も経過した後にようやく文革は間違っていたと表明しているとんでもない国である。まだまだ毛沢東を批判できるほどの土壌は出来ないのだろう。毛沢東を批判すると言う事は、中国共産党の存在自体を否定することになるからである。一党独裁の基盤を今後も続けていきたいと思っている共産党政権には、まず出来ないことだろう。神格化して、やってきたことはすべて伝説ということにしておいたほうが、後世に毛沢東を宣伝させるためには良い材料だと思う。最近の中国の紙幣は、すべて毛沢東の顔写真になってしまっている。それまでは中国にいる50の民族の顔を載せていたりしていたのだが、毛沢東批判に繋がらないようにするための意思表示だろうと思う。
1989年に有名な天安門事件が発生するが、これが「第2次」となぜ言われるのか、実はこの本を読むまで知らなかった。周恩来の死亡時にも、やはり天安門に民衆が集まり、軍の力で蹴散らした事件があったことがこの本で分かった。歴史は繰り返すとは言うが、1989年は民主化要求のデモであり、第1回目は4人組に対する反対デモであった。また、何度も政治的に失脚しているのにもかかわらず、後に党総書記に就任する鄧小平のこともここでは何度も出てくる。毛沢東は決して鄧小平を嫌っているわけではなく、政治的な闘争のために鄧小平を単に犠牲し、復活させるときには、周りのド肝を抜くようなポジションに持ってきて、本人のやる気を十二分に実力を発揮させたという、人の使い方に関しては卓越した能力を持っていたこともわかった。表向きの歴史は歴史としてしているべきであるが、その歴史が生んできた背景を知ることはなかなか中国の場合は難しい。難しいが決して知ることが出来ないというのではなく、こういう貴重な書類を通して実際に知ることが出来る。この本が嘘ではないという証拠は、すべてにおいて、事象・時間・心情の変化について矛盾点が存在しないことだろう。だいたいの嘘本は、矛盾する点が出てくるものだ。それがこの本には無い。無いと言う事は、すべて事実だからである。著者は毎日禁止されている日記を密かにつけていたことが、のちにこの本を出筆する際に大いに役立っているようだ。妄想ではここまで克明に書くことは出来ないだろう。
是非、中国を研究している人、中国が好きだと思っている人、自称進歩的思想家とおもっている馬鹿、中国が嫌いだと思っている、誰もが全員この本をまずは読むべきだと思う。

0 件のコメント:
コメントを投稿